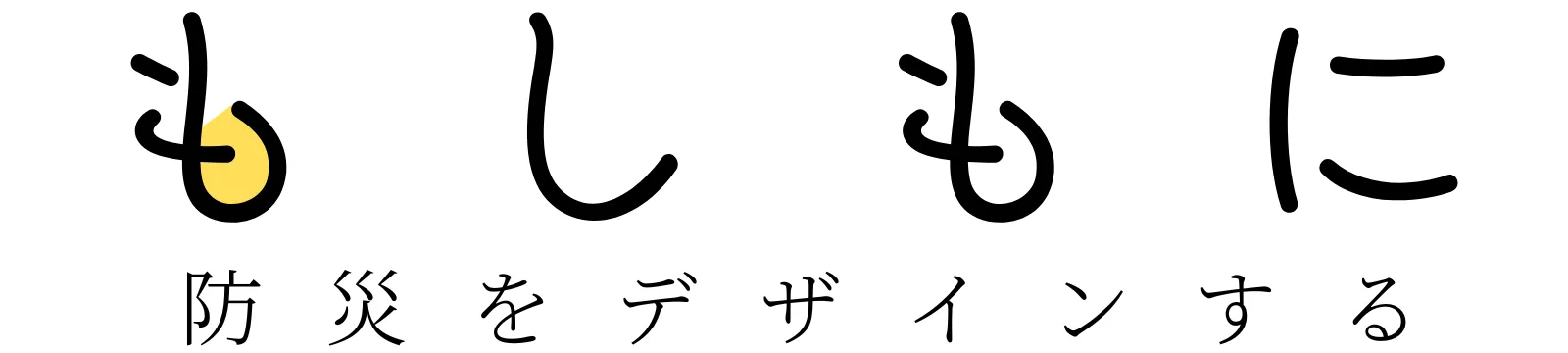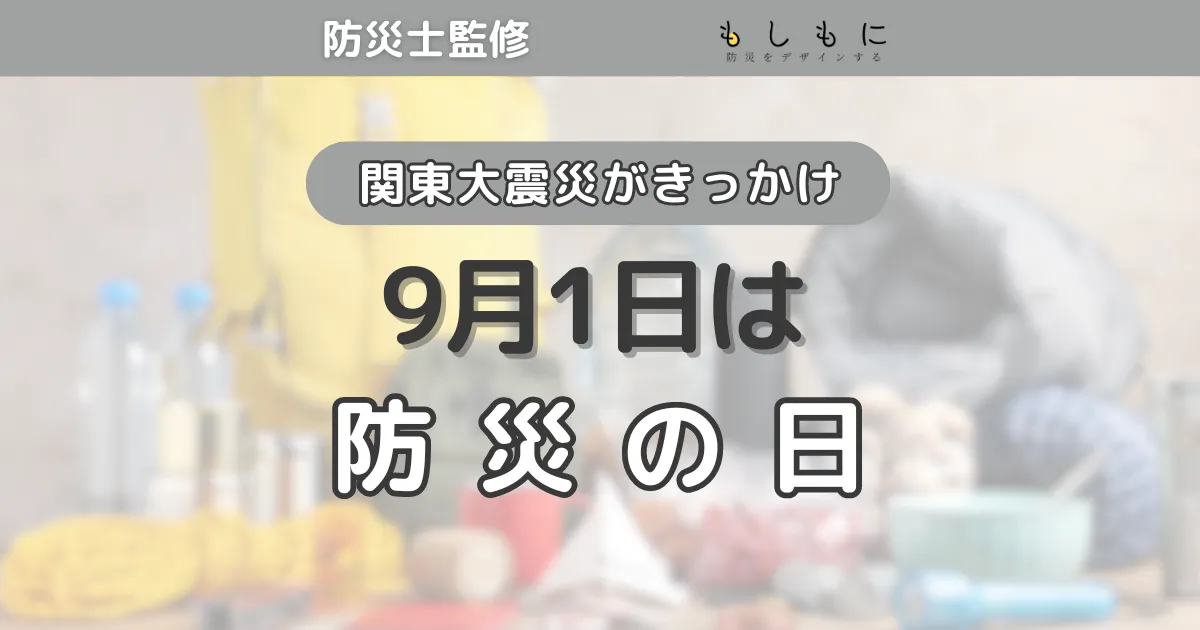こんにちは、もしもにスタジオ代表の防災士うめいです。
このサイトでは「防災をデザインする。」をテーマに防災に関するお役立ち情報を発信しております。
今回は「防災の日」についての記事です。
防災の日とは?2025年はいつ?
防災の日は、1923年9月1日に発生した関東大震災の犠牲者をしのび、災害からの復興を祈って1960年に内閣の閣議了解により制定されました。それ以降、「防災の日」は毎年9月1日に行われています。なお、防災の日は国民の休日ではありません。
9月1日を中心とした8月30日から9月5日までの期間は「防災週間」とされ、9月全体は「防災月間」となっています。
 もしもにゃん
もしもにゃん普段防災に興味がない人も、9月は一緒に防災について考えるにゃん~
2025年9月1日・防災の日は月曜日となってます。
なぜ9月1日が防災の日なのか?
前述のとおり、9月1日は1923年に関東大震災が発生した日です。関東大震災は、東京や横浜を中心に大きな被害をもたらし、多くの命が失われました。この出来事は日本にとって大きな教訓となり、防災の重要性を痛感するとともに、日本の防災の仕組みを大きく変えることにもなりました。



関東大震災では過去最大の10万人以上の方が命を落とした、日本災害史上で最悪の震災と言われているにゃん…
この震災の教訓を忘れずに再び同じような被害を避けるために、日本政府は1960年9月1日を「防災の日」と定めました。防災の日前後には、テレビや新聞・雑誌などを中心に多くのメディアが「防災」をテーマに取り上げて特集をします。とくに「民放NHK6局防災プロジェクト」として防災の大切さを地上波主要メディアが連携していることには注目です。
また、学校や職場、地域で防災の日前後に合わせて防災訓練が行われることもあります。避難経路の確認や避難所の運営方法、初期対応の訓練が行われることで、実際に災害が発生しても迅速な避難ができるようになります。同時に、各地で防災意識を高めるためのイベント・講演会・シンポジウムも開催され、防災に関する知識や技術が広まります。
さらに、防災の日前後(8月・9月)は「台風シーズン」と呼ばれています。毎年、日本は多くの台風に見舞われ、そのたびに大きな被害が発生します。台風を中心にした災害の多い9月だからこそ、防災の日を通じて、台風や地震、津波などの自然災害に対する準備と対応を見直すことができます。
防災の日に行われるイベント・子供向けのものも!
防災の日に行われるイベントは、「お楽しみ要素」も強く地域の結びつきを強めたり、防災を考えるきっかけづくりにはピッタリのイベントが多いです。大人も子どもも楽しいプログラムが用意されていることが多く、参加すれば「防災はカタくてつまらない」いというイメージが払拭できるでしょう。賞味期限間近の備蓄食などが無料配布されることもあり、おトクなことも多いです。家族全員で参加してみると、楽しく過ごせるかもしれません。
防災イベントの情報は、自治体の発行する地域情報誌などに掲載されることが多いので、ご自身の地域の情報誌をご覧ください。
少し時期がずれてしまいますが、内閣府が主催で、日本最大の防災イベント「ぼうさいこくたい」は例年、9月~11月に行われています。なお、今年のぼうさいこくたい2025については9/6(土)・9/7(日)に熊本で行われます。
防災の日は地域防災を見直して
防災の日は、メディアを中心に防災の特集やニュースが組まれますが、最終的には「自分ごと」にすることが大事です。災害対策と言えば、まずは個人でできる避難道具(防災リュック)や避難計画の見直しがありますが、防災の日をきっかけに、自分が住んでいる地域の防災イベントや集会に足を運んでみましょう。地域全体で防災力を向上していくことが大事です。



自分だけで準備を進めても助からないのが災害だにゃん。普段から地域の連携が大切だにゃん…!
地域防災をすすめるためには、地域の特性やニーズを汲み取った防災活動が重要です。
例えば、東京では首都直下型地震を想定した対策を中心に防災をすすめています。東京の中でも、細かい地域特性を考慮した情報発信が有効です。例えば、木造密集地域では火災時の避難などを中心としたテーマでのイベントや活動が良いでしょう。洪水時に区全体が水没すると言われている、東京都江戸川区などを中心に甚大な水害が予想される地域は『マイタイムライン』を活用したワークショップなども有効でしょう。
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌などの大都市圏では帰宅困難問題などがテーマになりそうです。
台風や豪雨が頻繁に発生する九州や西日本地方では水害対策に重点が置かれています。
中部地方の山間部では、土砂災害に対する取り組みが重要です。斜面の崩壊を防ぐための植林活動や、避難訓練が行われています。
西日本の太平洋側地域では南海トラフ地震を想定した避難計画やイベント・情報発信が盛んです。
東北・北陸・北海道などは、災害時の寒さ対策や豪雪対策などもポイントになりそうです。
このように、地域ごとの特性を考慮した防災意識の取り組みは、地域住民の安全を守るために不可欠です。防災の日のイベントや集まりを計画する際は、地域のニーズに合った防災活動を推進するとよいでしょう。地域に合わせた防災対策をすすめることで、実際に災害が発生したとしても被害を抑えることができます。
次年度の防災の日に向けて
単発のイベントで終わらせずに、継続的な意識づけを
一方、防災の日が過ぎ去ってしまうとメディアの防災特集は減り、防災イベントなどの開催も少なくなります。しかし、防災は継続的な取り組みが大事のため、単発のイベントで終わらせず次年度に向けた行動や計画などもしっかりと行っていきましょう。
例えば、防災教育の強化などは継続的な取り組みとして重要です。学校では、地震や火災、水害などに対する対策を授業に織り込む「フェーズフリーな授業」が注目されています。例えば、算数での津波到達時間の計算(時速36kmで進む津波から逃げる方法)や、社内の校外学習でハザードマップづくりをするなどです。ほかにも、日々の整理整頓を声掛けし、学校の美観を保つことも立派な防災です。
SNSを活用した情報取集の体制づくりも欠かさずに
さらに、最新の防災アプリやSNSを活用して、災害情報を迅速に共有できる環境をつくるようにしましょう。
東日本大震災の際は当時のツイッター(現X)を使った情報のやり取りが多く行われていました。しかし、現在のX(旧ツイッター)は「インプレゾンビ」と呼ばれる、無意味な情報拡散を繰り返す厄介な存在が蔓延っています。災害時、インプレゾンビに惑わされないためにも、普段から信頼できる情報源・フォロー先を確保しておくのも立派な防災です。
防災グッズのトレンドを確認しよう
防災の日には、防災グッズのトレンドをおさえておくのもおすすめです。特に、スマホが普及した現在ではひと昔前の防災グッズセットなどでは対応できなくなっているケースがあります。災害対策グッズについては、よく聞かれる質問なので、別の記事にまとめています。
もしご興味あれば以下の記事もあわせてご確認ください。
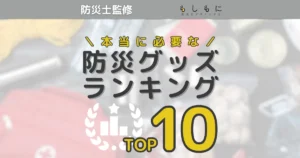
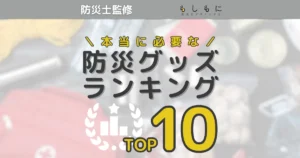
防災意識向上に役立つアプリやWebサービス
防災の日をきっかけに、スマホに入っているアプリを見直してみましょう。
NERV防災や、Yahoo天気、NHKニュース・防災アプリなどは必須で入れておきたいアプリです。また、「重ねるハザードマップ」や「地震10秒診断」を確認しておくのも良いでしょう。
防災の日まとめ
防災の日の意義は、過去の災害を振り返るだけでなく、未来の災害に備えるための準備を怠らないことにあります。自然災害はいつ、どこで発生するか予測が難しいですが、日常的に防災意識を持ち続けることが、いざという時に命を守るための大きな助けになります。9月1日「防災の日」は、このようにして日本における防災のシンボルとなり、大切な役割を果たし続けています。
地域ごとに異なる災害リスクに対応するため、コミュニティ全体での協力体制を強化し、災害に備えることが重要です。地域の防災訓練やイベントにみんなで参加し、お互いに支え合う意識を持つことで、災害に強い地域を作ることができます。防災の日を通じて安心して暮らせる地域づくりに向けた一歩を踏み出しましょう。